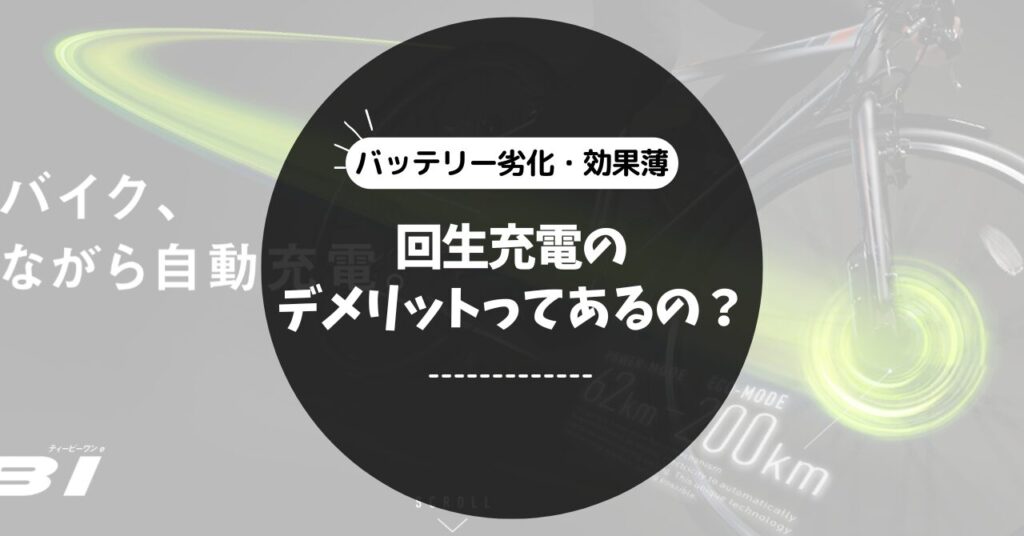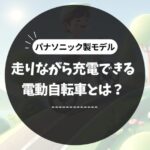電動自転車の回生充電ってデメリットあるの?
電動自転車の普及が進む中、エコで効率的な走行を実現するために「回生充電」という機能が注目されています。
回生充電は、ブレーキや下り坂で自動的に発電しバッテリーに電力を蓄える仕組みです。
この自動充電は一見便利な機能に見えますが、実際にはデメリットも少なくありません。
特に日常的な走行環境では効果が限定的で、バッテリー寿命にも影響を与える可能性があります。
例えば、ヤマハやパナソニックといった大手メーカーは回生充電機能を搭載しない選択をしています。
彼らは、頻繁な充電と放電がバッテリーの劣化を加速させるリスクや、回生充電の効果が限定的であることを理由により実用的なモデルの開発に力を入れています。
この記事では電動自転車における回生充電のメリットとデメリットを詳しく解説し、回生充電機能を選ぶ際の注意点について探ります。
電動自転車で回生充電を選ぶデメリット

自転車における回生充電とは
電動自転車の回生充電は、走行中にモーターを発電機として利用し、ブレーキや下り坂のタイミングで電力を生み出してバッテリーに蓄えるシステムです。
通常、モーターはバッテリーから電力を受け取ってアシスト機能を提供しますが、回生充電ではその逆にモーターが車輪の回転力を電気に変えてバッテリーに戻します。
自転車の回生充電は、特に下り坂で速度がついているときや、ブレーキを使用して減速する場面で主に活用されます。

このため、平地を走行している時には、ほとんど電力を回収できません。
さらに回生によって回収できる電力量は非常に小さく、自動車などのハイブリッド車と比べて発電効果は限定的です。
メリット
回生充電の最大のメリットは、走行中に一部のエネルギーを再利用できることです。
これにより、バッテリーの消費を抑え、走行可能距離をわずかに伸ばすことが可能。
特に、長い下り坂や連続したブレーキングが発生するような状況では、多少のバッテリー回収ができるため、エコな移動手段としての評価が高まります。
また、環境に配慮した技術として、使ったエネルギーを一部回収して再利用することで、の充電頻度を減らす助けにもなります。
これがエコロジー意識が高いユーザーや長距離移動をする利用者にとっては大きなメリットです。
前輪回生充電システム
回生充電には前輪と後輪の二種類が存在します。
前輪回生充電システムは、前輪に搭載されたモーターを利用して発電する機能。
このシステムではブレーキをかけたときに回生充電が開始され、前輪の回転力を電力に変換してバッテリーに戻します。
通常、時速6km/hから24km/hの範囲で充電が行われ、速度が低すぎたり高すぎたりすると充電は行われません。
前輪回生システムの大きなメリットは、走行安定性です。
前輪にモーターを搭載することで、アシスト機能も前輪で行われるため、特に滑りやすい路面や坂道での安定性が向上します。
また、ペダルをこいでいない間も、惰性で前輪が回転することで発電が行われますが、その分走行中にわずかな抵抗が発生し速度が落ちやすくなることがあります。
後輪回生充電システム
後輪回生充電システムでは、後輪のモーターを使って電力を回収します。
このタイプの特徴は、ブレーキをかけなくても、一定の速度に達すると自動的に充電が始まることです。
例えば、時速20km/h以上になると、下り坂や惰性走行中にモーターが発電を開始し、バッテリーに電力を蓄えます。
後輪回生システムの利点は、高速走行時にも回生充電が可能な点です。
特に、長い下り坂や急な坂道では回生ブレーキが働くため、ブレーキパッドの摩耗を抑えつつ、安全に速度をコントロールできます。
しかし、このシステムではユーザーが充電のタイミングをコントロールできないため、平地での走行時に自動的に充電が始まり、速度が落ちてしまうという不便さがあります。
自動充電はそこまで機能しない
自動充電がどの程度機能するかについては実際の効果は限定的。
この仕組みが理論的には魅力的であっても、日常的な使用ではその期待に対してがっかりすることも少なくないんです。
まず自動充電が有効に機能するのは、主に長い下り坂やブレーキを多用する状況に限られること。
例えば、標高の高い場所から低い場所に向かって下り続ける場面では、電動自転車のモーターが発電機として機能し、その回転力を電力に変換してバッテリーに充電します。
このような条件下では、ある程度の電力を回収することができ、バッテリーの持ちがわずかに延びる効果が期待できます。
しかし、このような場面は実際の利用シーンでは少ないため、普段の通勤や買い物、平地でのサイクリングなどの日常的な使用では、この充電システムが十分に活用されることはほとんどありません。
街乗りで使う人はほとんど効果がないことも
なので平地や短い下り坂では自動充電の効果は非常に限定的。
自動充電が機能するためには、自転車が一定の速度を維持して走行する必要があります。
ではモーターが発電機として稼働する機会が少なく、たとえ短い下り坂で回生充電が作動したとしても、回収される電力はごくわずかです。
そのため、日常の平坦な道を走ることが多い場合や、長い下り坂があまりない環境では、回生充電がほとんど役に立たないというケースが多く見られます。
「走りながら充電できる」というイメージを抱いているとその効果の少なさに失望することになるかもしれません。
バッテリー寿命に影響を及ぼすことも
回生充電は一見エコな機能に見えますが、頻繁に行われるとバッテリーに負荷をかける可能性もあります。
これはバッテリーが充電と放電を繰り返すことで徐々に劣化していく性質を持っているから。
特にリチウムイオンバッテリーの場合、充放電サイクルが多ければ多いほど、バッテリー内部の化学反応が劣化を引き起こし、最終的にはバッテリー容量が減少し稼働時間が短くなる原因となります。
回生充電は、この充放電のサイクルを加速させる要因となるため、効果的に活用するためにはその使用頻度に注意が必要です。
Li-ion 電池はサイクル寿命が短いため,回生充電による充電頻度の増加は寿命低下を招く。
電気二重層キャパシタを用いた電動自転車の 回生時の電力損失の比較
また、バッテリーの寿命は「サイクル寿命」と呼ばれ、これは充電と放電を1サイクルとして計算されます。
一般的にリチウムイオンバッテリーのサイクル寿命は、数百から千回程度とされていますが、頻繁な回生充電によってこのサイクルが早く回ると、サイクル寿命が短くなります。
つまり、バッテリーの「使える寿命」が短くなり、結果的に早い段階でバッテリーの交換が必要になる可能性があるということです。
効果的な使い方のポイント
ただし使い方によっては劣化を防ぎながら回生充電を活用することもできます。
例えば、バッテリーがほぼ満充電の状態で回生充電が繰り返されると、過充電のリスクが高まります。
なので効果的に回生充電を活用するためには、バッテリーの残量を確認し、必要以上に充電を行わないよう管理することが求められます。
また、坂道を頻繁に走る場合やブレーキを多用するような環境での使用では、バッテリーへの負荷がかかりやすいため、適度な頻度で回生充電を活用することが推奨されます。
必要以上に回生充電を期待するのではなく、あくまで補助的な機能として位置づけ、過剰な充電を避ける使い方がバッテリーの寿命を長持ちさせるための鍵となります。
速度が出ないと充電されない:前輪
前輪モーターを使った回生充電の場合、一定の速度が出ないと充電が開始されません。
たとえば、時速6km/hから24km/hの間でのみ充電が機能するモデルが多く、速度が低すぎたり高すぎたりすると充電がされないという制約があります。
したがってこの速度範囲に収まるのは、主に平地や緩やかな下り坂での中速走行時です。
しかし、日常の自転車の使用環境では信号や交差点での停止や、スピードを出すことが難しい狭い道などが多いため、この理想的な速度域で走る機会は少なくなります。
普段の通勤や買い物といった用途では、回生充電が機能するタイミングは非常に限られているため、期待していたほどの充電効果が得られないことが多いです。
たとえば、頻繁にストップする信号待ちの多い通勤経路では、時速6km/h未満の速度がしばしば発生するため回生充電が作動しない時間が長くなるなど。
効果を最大限に発揮するには、速度を維持しやすい中速域での長時間走行が必要ですが、これは日常生活ではあまり実現しにくい条件になっています。
勝手に充電が始まる:後輪
後輪モーターを搭載した電動自転車の場合、回生充電はブレーキをかけたときではなく、特定の条件下で自動的に始まります。
この自動充電はユーザーが意図しないタイミングでも作動し、特に時速20km/hを超えると平地でも勝手に充電が始まることがあります。
このため、惰性で走りたい場合でも速度が抑えられてしまい、スムーズな走行が阻害される可能性があります。
後輪回生充電の最大の問題点はこのユーザーが充電のタイミングをコントロールできないことです。
前輪モーターの回生充電では、ブレーキ操作に連動して充電が開始されるため、充電のタイミングはユーザーの操作に依存します。
しかし、後輪モーターの自動充電システムでは、速度や条件に応じて勝手に充電が始まるため、ユーザーが意図的に制御することが難しいのです。
このため、平地や長い下り坂でスピードを維持したい場面でも、自動的に充電が始まり、減速してしまうことがあります。
このように、走行中に回生充電のタイミングを自分でコントロールできないことは、特に速度を維持して移動したいユーザーにとっては大きなストレスとなります。
このように、回生充電は便利な側面もありますが、状況によってはデメリットが目立つこともあります。
電動自転車の回生充電におけるデメリット対策

ライフスタイルに合ったモデルを選ぶ
電動自転車の回生充電機能は使用環境やライフスタイルによってそのメリットとデメリットが大きく変わります。
そのため、自分のライフスタイルに合ったモデルを選ぶことが、回生充電によるデメリットを避けるための最初の重要なステップです。
このような人は回生充電のデメリットをほとんど感じないでしょう。
まずは長い下り坂や坂道が多い地域で頻繁に走行する場合、回生充電機能が最大限に活用されバッテリーの消費を抑えることができます。
このような地域では、回生充電付きのモデルが効果的です。
しかし、平坦な道が多い都市部や、頻繁にストップ&ゴーが発生する通勤路では、回生充電の機会が限られているためその機能の恩恵を十分に受けることが難しい場合があります。
さらに、速度を維持できるかどうかも選択のポイントです。
前輪モーターの回生充電モデルの場合、時速6km/hから24km/hの速度で走行しないと充電が行われないため、この速度域を維持しやすいルートや走行スタイルを持つ人には向いています。
しかし、信号が多い道や混雑した道を走ることが多い場合、回生充電が作動しない時間が長くなるため回生充電のないモデルの方が適しているかもしれません。
ただ坂道を走る場合は工夫すれば楽に、スピードを出しながら登ることもできます。
そのコツなどは以下のページでまとめてるのでよかったら合わせてどうぞ。
ヤマハのオススメモデルと設定
そんなライフスタイルが合えばとても便利な回生充電ですがヤマハの電動自転車には付属していません。
どの自転車も残念ながら回生充電機能はありません。
ヤマハが回生充電を使わない理由は主にコスパの面が大きいと予想されます。
ヤマハの電動自転車は主に後輪駆動を採用していますが、回生充電システムは主に前輪ハブモーターで実装されることが一般的です。
後輪にモーターを搭載した場合、回生充電の効率が悪くなることが知られています。
ヤマハが使用しているセンターモーター(後輪駆動)は、回生充電に適していないため技術的な面でも回生充電を避けていると考えられます。
また、回生充電システムを搭載するにはモーターやバッテリー、コントローラーの設計が複雑化し、製造コストが上がる可能性があります。
回生充電に対応するための追加の部品が必要になることで、故障のリスクが高まり、メンテナンスコストも増える可能性があります。
これらの理由からヤマハはいまだに回生充電機能を実施していないと予想しました。
パナソニックのオススメモデルと設定
パナソニックの回生充電自転車はビビ・チャージというものがあります。
ただこのモデル、すでに販売終了しています。
いまだに取り扱いがある販売店はあるもののパナソニック公式からは販売していません。
その後継モデルも出ていなく、最新の回生充電自転車が不在となっています。
理由は公表されていないもののヤマハと同じくコスパやビビ・チャージの売れ行きがそれほど良くなかったからかもしれません。
ブリジストンのオススメモデルと設定(走りながら自動充電)
ブリジストンには全てで11種類の回生充電モデルが存在します。
中でもオススメなのはTB1eというモデルです。

これは全11種類の中でも二番目に安い価格をしています。
さらにバッテリー容量も多く、エコモードで最大200キロの連続走行ができます。
なので一定速度を出さないといけない回生充電ととても相性が良くなっています。
スポーツタイプなので街乗りでもサイクリングでも使えるマルチなモデルです。
回生ブレーキの自作は非推奨
回生ブレーキの仕組みはモーターを発電機として利用し、ブレーキをかけた際に車輪の回転力を電力に変換してバッテリーに蓄える技術です。
これによりエネルギーの再利用が可能になりますが、このシステムは非常に複雑であり、正確な制御と安全性が必要。
ということで個人での自作や改造は非推奨です。
その理由の一つは、電動自転車の回生ブレーキシステムは、高度な技術と専用の部品を使用して設計されているため、正確なバランスと制御が求められるからです。
自作した回生ブレーキシステムでは、ブレーキの制動力や発電量が不安定になり、予期しないタイミングでのブレーキ作動や充電不足などの問題が発生する可能性があります。
また、過充電や過放電が発生すると、バッテリーの寿命を大幅に短縮したり、最悪の場合は火災や事故の原因にもなりかねません。
さらに、電動自転車の回生ブレーキシステムは、各メーカーが長年にわたってテストと改良を重ねた結果として生まれたものです。
そのため、個人での改造や部品の変更は、メーカー保証が無効になるリスクも伴います。
市販のパーツを使って回生充電やブレーキシステムをカスタマイズしようとすることは、安全性の面でも推奨されません。
したがって、回生ブレーキや充電システムに関しては、信頼できるメーカーの既製品を使用するのが安全であり、自作や改造は避けるべきです。