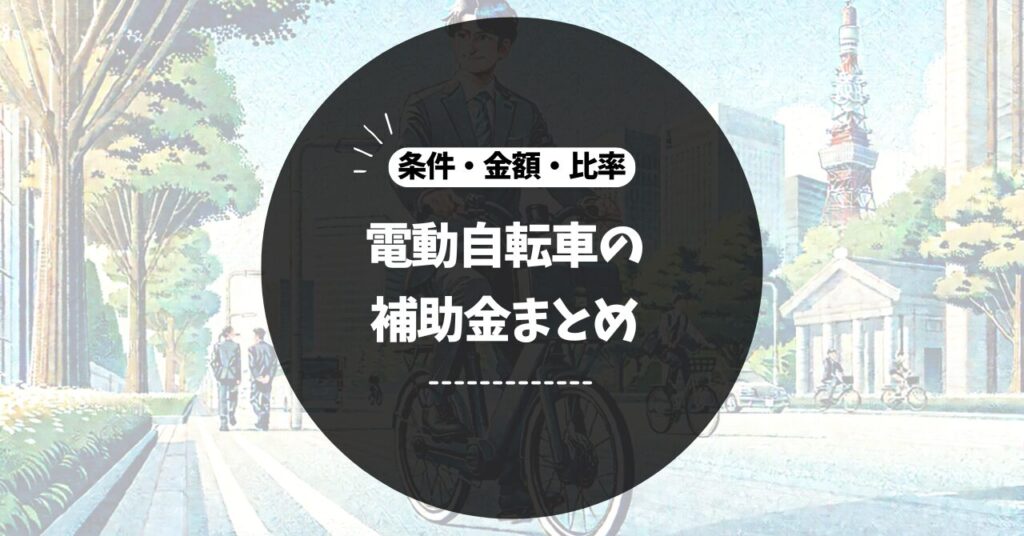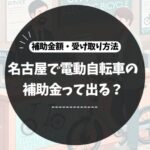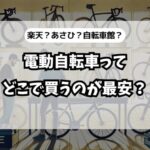電動自転車買うと補助金貰えるって本当?
「電動自転車って便利だけど、ちょっと高いな…」と感じたことはありませんか?実は、そんな悩みを解決してくれるのが「電動自転車 補助金」の存在なんです。
特に子育て中の家庭や、高齢者の方にとっては、移動手段としてとても頼りになる電動アシスト自転車。
東京都をはじめ、全国の自治体で導入が進んでおり、「いくらもらえるの?」「どういう条件?」といった疑問の声も多数!この記事では、電動自転車に対する補助金の種類や対象、実際の金額、高齢者や都内での制度の違いなど、わかりやすく解説していきます。
電動自転車の補助金について詳細解説

電動アシスト関連の制度一覧
電動アシスト自転車に関する補助制度は、国が一律に行っているものではなく、各自治体が独自に設けている制度です。そのため、対象者や補助対象となる自転車の種類、補助金額、申請方法まで自治体ごとに異なります。制度の目的に応じて、大きく3つのカテゴリに分けられます。
- 子育て支援を目的とした補助制度
- 高齢者支援を目的とした補助制度
- 自転車用ヘルメット購入補助制度
1. 子育て支援を目的とした補助制度
この制度は、小さなお子さんを育てている家庭の移動負担を軽減し、育児をサポートする目的で導入されています。特に以下のような条件が設けられている自治体が多く見られます。
- 未就学児を2人以上養育していること(対象となるのは1歳以上から就学前の子ども)
- 購入する自転車は「幼児2人同乗基準適合車」および「BAAマーク(安全基準)」付きであること
- 市区町村内に住民登録があること
- 対象の店舗(多くは地元の実店舗)で新品を購入すること
- 防犯登録済であること
- 市税や保育料などの滞納がないこと
さらに、補助制度の利用は「1世帯あたり1回限り」と制限されている場合もあります。中には、事前申請が必要な自治体もあるため、購入前の確認が非常に重要です。
2. 高齢者支援を目的とした補助制度
高齢者の交通安全や移動手段の確保を目的とした補助制度です。特に高齢ドライバーによる事故が社会問題となっている背景もあり、「運転免許証の自主返納」を条件に導入している自治体が増えています。
代表的な条件には以下のようなものがあります。
- 対象年齢は65歳以上または70歳以上
- 有効期限内の運転免許証を自主返納していること(1年以内など期限付き)
- 地元の販売店で新品の電動アシスト自転車を購入
- 交通安全講習や自転車利用講習会の受講が必要
- 市税などの滞納がないこと
補助内容も手厚く、購入金額の25~75%を補助してくれる自治体もあります。つくば市などでは最大12万円の補助が出るなど、高齢者の生活の質を高める大きな後押しとなっています。
3. 自転車用ヘルメット購入補助制度
2023年4月から、すべての自転車利用者にヘルメット着用が「努力義務」とされたことを受け、各自治体ではヘルメットの購入に対する補助制度を設けています。
この制度の特徴は以下の通りです。
- 対象は自転車乗車用ヘルメット(安全基準に適合しているもの)
- 購入証明(レシートや領収書)が必要
- 中古品やフリマアプリでの購入は対象外
- 還元方法はキャッシュレスポイントやプリペイドカードが主流
- 購入日や購入店が限定されている場合もある
補助金額は数千円程度が多く、自治体によっては1人あたりの補助回数や補助上限金額も設定されています。
いくら出るのか
電動アシスト自転車の補助金額は、自治体によって支給方法や金額が大きく異なりますが、相場としては1万円〜3万円の範囲が一般的です。ただし、以下のように「定額支給」と「補助率による支給」に大きく分類されます。
1. 定額で支給されるパターン
この方式では、購入金額にかかわらず、あらかじめ定められた金額が支給されます。たとえば、
- 一律10,000円支給
- 一律15,000円支給
- 一律30,000円支給
など、購入するモデルや値段に関係なく、上記の額が補助されるため、わかりやすく利用しやすい制度です。ただし高額なモデルを購入する場合、実質的な補助割合は下がる点には注意が必要です。
2. 購入金額に応じた補助率で支給されるパターン
こちらは購入金額に対して一定の割合で補助金が支給される方式で、以下のような補助率が一般的です。
- 補助率:20%(5分の1)
- 補助率:25%(4分の1)
- 補助率:33%(3分の1)
ただし、多くの自治体では「補助上限額」も併せて設定されています。つまり、補助率で計算した金額が上限額を超えた場合は、上限額までしか支給されない点に注意が必要です。
- 自転車の購入価格が10万円
- 補助率:20%(2万円相当)
- 補助上限:15,000円
この場合、補助金として実際に受け取れるのは「15,000円」までとなります。補助率での計算金額が高くても、上限額を超えているとカットされます。
3. 高額補助の事例も存在
一部自治体では、特別な条件(高齢者、免許返納者、環境活動参加者など)を満たすと、さらに高額な補助が受けられるケースもあります。たとえば、
- 茨城県つくば市:3輪・4輪電動自転車なら上限12万円まで補助
- 三重県伊勢市:本体価格の3分の1、上限3万円まで補助
など、特定条件に合致する場合、より大きな金額の補助を受けられる制度もあります。
4. 複数の補助制度が併用できるケース
自治体によっては、電動自転車本体への補助に加えて、ヘルメットの購入費や保険加入費、講習会参加費などにも補助を出している場合があります。これらを組み合わせることで、実質的な自己負担額をさらに抑えることが可能です。
金額に対する補助率
電動アシスト自転車の補助制度でよく出てくる「補助率」とは、購入金額に対して、どれだけの割合で補助金が出るかを示す数値です。これは補助金の金額を算出する基準になるもので、多くの自治体では以下のような補助率が使われています。
主な補助率の例
- 20%(5分の1)
10万円の自転車を購入した場合、20%なら補助金額は2万円 - 25%(4分の1)
10万円の自転車に対して、補助額は2万5,000円 - 33%(3分の1)
10万円なら3万3,000円が本来の補助額
ただし、これらの補助率がそのまま全額支給されるわけではありません。
自治体ごとに「補助金の上限額」が定められているため、計算された補助額が上限を超える場合は、その分が切り捨てられます。
たとえば、
- 補助率が33%でも、上限額が15,000円であれば、それ以上の補助は受けられません。
- 仮に3万円の補助が算出されても、支給されるのは15,000円までとなります。
このため、「補助率が高い=多く補助が受けられる」とは限らず、「上限額」とのバランスを理解しておくことが重要です。
| 項目\購入金額 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 |
|---|---|---|---|
| 補助率 | 33% | 25% | 20% |
| 計算上の補助額 | 26,400円 | 25,000円 | 24,000円 |
| 補助金の上限額 | 30,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
| 実際に受け取れる補助額 | 26,400円(満額) | 15,000円(上限) | 20,000円(上限) |
限額に注意が必要です。
高齢者の場合
高齢者を対象とした電動アシスト自転車の補助制度は、高齢者の移動手段の確保や安全な交通環境の実現を目的として、全国の一部自治体で導入されています。運転免許証の自主返納を促進し、交通事故のリスクを減らすと同時に、高齢者の自立した生活や外出機会を支援する重要な取り組みです。
高齢者の場合は以下のような条件をすべて満たす必要があります(自治体により若干の違いあり)。
- 対象年齢:65歳以上または70歳以上
- 運転免許証の自主返納が済んでいること
- 市や自治体が実施する「交通安全講習」や「自転車講習」の受講が必須
- 市税、国保税、介護保険料などの滞納がないこと
まず、対象年齢は65歳以上または70歳以上とされており、自治体によって基準は異なるものの、概ね65歳から利用できる場合が多いです。そして、運転免許証の自主返納が済んでいることが求められますが、この際には有効期限内の免許を返納し、通常は返納から1年以内に申請しなければなりません。
さらに、市や自治体が実施している「交通安全講習」や「自転車講習」を受講することも必須条件となっており、安全に利用できる知識と技術を身につけたことが確認される必要があります。加えて、市税や国民健康保険税、介護保険料などの公的な税金・保険料に滞納がないことも重要で、これに違反していると補助の対象外となるため、事前に納付状況を確認しておくことが大切です。
自治体による補助内容の違い(具体例)
① 茨城県つくば市(全国でも屈指の手厚い補助)
- 対象:満70歳以上、市内在住、交通安全講習受講者
- 補助率:購入価格の75%
- 上限額:
- 2輪車:5万円まで
- 3輪・4輪車:12万円まで
- 備考:千円未満切り捨て、年度内の講習会参加者が対象
→ 例:3輪の電動自転車(16万円)を購入した場合
75%=12万円 → 上限に達するため、満額12万円が支給される
② 愛知県豊橋市
- 対象:70歳以上で運転免許を自主返納済、市税滞納なし
- 補助率:購入金額の1/4(25%)
- 上限額:15,000円
- 条件:とよはしエコファミリーに登録する必要あり
→ 例:電動自転車が8万円の場合
25%=20,000円 → 上限が15,000円なので、15,000円支給
③ 三重県伊勢市
- 対象:65歳以上、市税・保険料の滞納なし、安全利用講習会受講者
- 補助率:33%(3分の1)
- 上限額:30,000円
申請前には講習会の予約や運転免許の返納証明書の取得、さらに購入予定の店舗が補助対象かどうかの確認など、事前準備が必須となります。
そして、補助の対象となる自転車は新品に限られており、中古品や個人売買による購入は基本的に認められていません。また、補助制度の多くは地元の販売店での購入に限定されており、ネット通販で購入した場合は対象外となる自治体が多い点にも注意が必要です。
電動自転車の補助金【各都道府県別】

愛知県(名古屋市)
名古屋市では2024年現在、電動アシスト自転車の購入に対する補助制度は実施されていません。ただし、自転車関連の支援として「自転車用ヘルメットの購入補助制度」があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電動アシスト自転車購入補助 | なし (補助制度は実施されていません) |
| ヘルメット購入補助 | ● 補助率:購入費の1/2 ● 上限額:2,000円 ● 条件:名古屋市民であること、1人1回限り申請可能 |
| ゼロエミッション車 (EV・PHEV・FCV)補助 | ● EV:10万円 ● PHEV:5万円 ● FCV:20万円 ● 条件:名古屋市在住、対象車両の新車購入など |
これは、購入費用の2分の1(上限2,000円)を補助するもので、名古屋市民1人につき1回限りの申請が可能です。また、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池車(FCV)などのゼロエミッション車には最大20万円の補助金が支給されています。
一方、名古屋市以外の愛知県内では、蒲郡市が上限15,000円(補助率1/3)、岩倉市が上限25,000円(補助率1/2)の補助制度を設けており、条件を満たせば電動アシスト自転車の購入に補助が適用されます。
| 項目 | 蒲郡市 | 岩倉市 |
|---|---|---|
| 補助上限額 | 15,000円 | 25,000円 |
| 補助率 | 1/3 | 1/2 |
| 主な条件 | 市内在住 市内店舗で購入 防犯登録など | 市内在住 市内登録販売店で購入 子ども2人以上の親権者 など |
東京都(2024年・2025年の違い)
東京都における電動アシスト自転車の補助金制度は、2024年時点では東京都全体としての統一的な制度は存在していないものの、区ごとに独自の制度を設けているケースがあり、特に葛飾区では注目されています。
というのも、葛飾区では子育て世帯を対象に、未就学児が1人以上いる家庭が区内の自転車販売店でBAAマークや幼児2人同乗基準適合車マーク付きの電動アシスト自転車を購入した場合、購入金額の50%、上限5万円の補助が受けられる仕組みを設けているからです。
ただし、ネット購入は対象外であり、過去3年以内に同制度を利用していないことが条件となっています。
その一方で、江戸川区、板橋区、世田谷区、目黒区、大田区など、他の多くの区では現時点で電動アシスト自転車本体への補助制度は実施されていませんが、子育てや環境政策の観点から、今後制度が導入される可能性も指摘されています。
また、電動自転車本体への補助は少ないものの、自転車関連ではヘルメット購入に対する補助制度が都内広域で実施されています。これは、2023年からの道路交通法改正でヘルメット着用が努力義務となったことを受け、各自治体が安全対策として制度を設けているためであり、補助率は購入金額の50%、上限2,000円〜3,000円程度であることが多く、千代田区、文京区、世田谷区、練馬区、調布市、立川市、武蔵野市などで実施中です。
こうした状況から、東京都における電動アシスト自転車や自転車関連の補助制度は、区によって実施状況や内容が大きく異なるため、購入を検討する際は住民票のある自治体の公式情報を確認し、購入前に対象商品や申請方法などをしっかり把握することが大切です。また、今後補助対象が拡大される可能性もあるため、定期的に自治体の制度情報をチェックすることが望まれます。
大阪府
大阪府では、電動アシスト自転車に対する府全体での補助金制度は確認されていませんが、一部の市町村、特に泉大津市では独自の支援制度が実施されています。その泉大津市では、子育て世帯を対象に手厚い補助が用意されており、具体的には市内に居住し、未就学児を2人以上養育または生計を共にしている家庭が対象となっています。
さらに、申請者や同一世帯内に市税等の滞納がないことや、過去に同様の補助を受けていないこと、市が実施する環境保全事業や家庭のエネルギー調査に協力できることなどが補助を受けるための条件に加えられています。また、補助金額は電動アシスト機能付きの幼児2人同乗用自転車に対して最大45,000円が支給され、非電動タイプでも最大30,000円が補助されます。加えて、市内の自転車販売店で購入した場合にはさらに5,000円が上乗せされる仕組みになっており、地域経済の活性化にもつながっています。
補助を受けるには、購入費に関する領収書や保証書、防犯登録カード、各種安全基準マーク(BAA、SG、幼児2人同乗基準適合車)を確認できる写真の提出が必要であり、ヘルメットの写真も求められます。なお、対象となる自転車は新品に限られ、購入後は定められた期間内に申請手続きを完了させる必要があります。
このように、大阪府では府レベルでの補助は実施されていないものの、泉大津市のように市町村単位で具体的かつ実用的な補助制度が進められており、今後も他の地域に制度が拡大する可能性があるため、常に最新情報を各自治体の公式サイトなどで確認することが重要です。
埼玉県
埼玉県全体としては、電動アシスト自転車の購入に対する補助制度は設けられていません。
しかしながら、さいたま市と熊谷市では独自の補助制度を実施しています。さいたま市では、幼児2人同乗用電動アシスト自転車の購入費用の50%(上限30,000円)を補助する制度があり、さらに子ども用ヘルメット2個が進呈されます。
- さいたま市:1歳以上の幼児を2人以上養育している世帯を対象に、電動アシスト自転車の購入費用の50%(上限3万円)を補助
- 熊谷市:未就学児を2人以上養育している世帯に対し、電動アシスト自転車の購入費用の50%(上限3万円)を補助
- ふじみ野市:詳細な条件は確認が必要ですが、電動アシスト自転車の購入に対して最大10万円の補助を提供
この制度の対象となるのは、1歳以上で小学校入学まで1年以上ある子どもが2人以上いる世帯であり、市税の滞納がないことや、自転車安全講習会の受講が求められます。
また、熊谷市でも同様に、幼児2人同乗用電動アシスト自転車の購入費用の50%(上限30,000円)を補助する制度があり、申請の1年以内に購入した自転車であることや、市税・保育所保育料・放課後児童クラブ保育料の滞納がないことが条件となっています。
神奈川県
神奈川県全体では、電動アシスト自転車の購入に対する補助制度は設けられていません。しかし、厚木市では独自の補助制度を実施しています。この制度では、幼児2人同乗用自転車の購入費用の2分の1(上限16,000円)を助成します。 厚木市公式サイト
主な条件:
- 厚木市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
- 申請者が厚木市に住民登録されていること。
- 16歳以上で、小学校就学前の幼児を2人以上養育していること。
- 市が主催する幼児2人同乗用自転車講習会に参加していること。
- 本人および同一世帯の者が市税を滞納していないこと。
さらに対象となる自転車は、まず一般社団法人自転車協会が定める安全基準に適合し、BAAマークおよび幼児2人同乗基準適合車マークが貼付されていることが条件となります。
そして、これらの自転車は厚木市内の事業協力店で購入する必要があり、購入後には防犯登録を済ませた上で、TSマーク(赤または青)を取得しなければなりません。これにより、安全性や地域経済への貢献も考慮された制度設計となっています。
さらに、この制度を利用するためには、申請手続きを段階的に進める必要があります。最初に、市が主催する幼児2人同乗用自転車講習会を受講することが求められ、その受講から14日以内に必要書類を添えて助成金の交付申請を行う必要があります。
その後、交付決定通知を受け取ってから、自転車の購入に進みます。この際、購入はあくまで市内の事業協力店で行い、防犯登録およびTSマークの取得を行った上で、購入が完了した後に所定の期日までに助成金請求手続きを済ませる必要があります。
このような一連の手続きは、厚木市が子育て世帯に安全かつ実用的な移動手段を提供することを目的としており、制度全体を通じて、地域における交通安全と子育て支援の両立が図られている点が特徴です。
京都府
京都府においては、2025年4月時点で個人(一般家庭)を対象とした電動アシスト自転車の購入に対する補助制度は設けられていません。つまり、子育て世帯や高齢者といった個人が電動自転車を購入する際に利用できる公的な助成金制度は、現時点では京都市を含む府内の各市町村でも確認されていない状況です。
しかしながら、福祉や医療分野に関わる特定の事業者に対しては、京都府が独自に補助金制度を設けています。それが「訪問リハビリ等支援事業」と呼ばれる制度であり、訪問リハビリテーションを行う事業所が新たに開設または拡充を行う際に、電動アシスト自転車の購入費用が補助の対象となります。
この制度では、府内全域で新たに事業所を開設する場合は、購入経費の2分の1を上限150万円まで補助される一方で、丹後地域や中丹地域に所在する既設の事業所が拡充を行う場合には、補助率は同様に2分の1ながら上限が50万円までと設定されています。対象経費には、自転車本体の購入費用だけでなく、その保険料も含まれており、制度の目的は地域医療や福祉サービスの拡充と利便性の向上にあります。
ただし、この補助金はあくまで事業用の利用に限られ、一般個人の生活用電動自転車の購入には使えないことに注意が必要です。今後、全国的な補助制度の拡充に伴って、京都府でも個人向けの電動アシスト自転車補助制度が導入される可能性はありますので、定期的に京都府および市町村の公式サイトを確認しておくことが推奨されます。