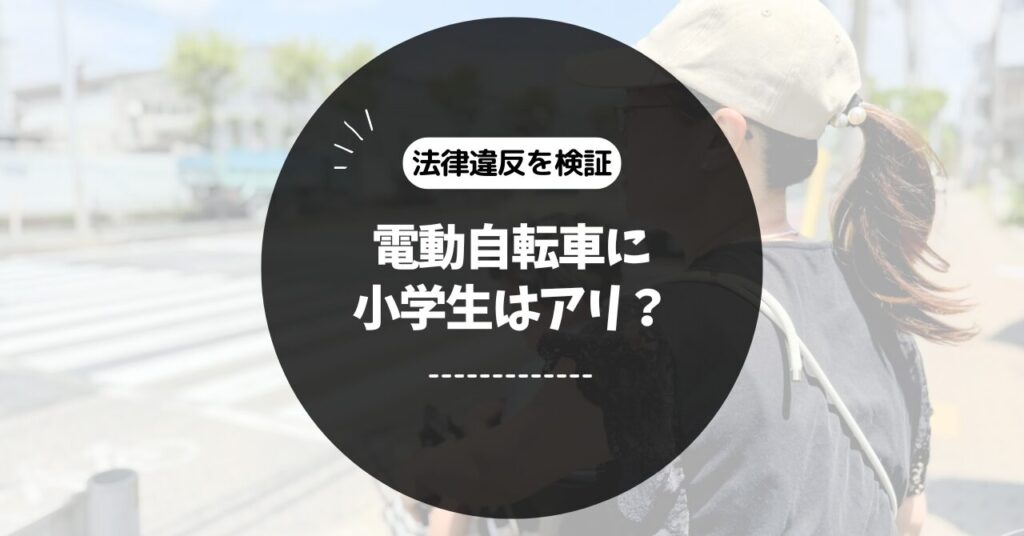電動自転車に小学生乗せるのダメって本当?
ペダルが楽な電動自転車に子供を乗せるととても移動が楽になります。
ただ小学生以下とそれ以上とでは法律が変わることをご存じでしょうか。
場合によっては罰金、違反となる場合も。
ということで今回は電動自転車に小学生は乗せられるのかを検証。
電動自転車で小学生を乗せるのは違法?

電動自転車に小学生を乗せることは多くの親にとって意外に感じるかもしれませんが、実は法律で禁止されています。
小学生を電動自転車に乗せることが禁止されている理由
電動自転車に小学生を乗せることが法律で禁止されている理由は安全性に深く関わっています。
電動自転車は通常の自転車に比べてモーターによるアシスト機能があるため、重い荷物や幼児を乗せることに適した設計です。
しかしこれが「小学生以上」になると体重や身長が幼児よりも大きいため、自転車の重量が増え操作が難しくなることが問題視されています。
自転車の重量バランスが崩れると転倒しやすくなり、事故が起きる確率が高まります。
特に電動自転車はパワーがあるため、加速やブレーキが通常の自転車よりも敏感。
大きな子どもを乗せた状態で急ブレーキをかけた場合、前後の重量バランスが崩れて転倒する危険性が非常に高くなります。
さらに、乗っている子どもが自転車の衝撃に対して受けるダメージは幼児よりも大きくなるため、安全面から法律で制限されています。
東京都道路交通規則ではこのようなリスクを軽減するために「幼児用座席に乗せることができるのは小学校就学前まで」と定めており子どもの安全を第一に考えた規制となっています。
東京都道路交通規則の具体的な内容
東京都道路交通規則では電動自転車の幼児用座席に乗せることができる子どもの年齢制限を明確に定めています。
(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させるとき。
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html
この規則では「小学校就学の始期に達するまでの者」とされており、これは基本的に6歳未満の幼児を指します。
つまり小学校に入学する年齢になると、幼児用座席に座らせることが法律違反となります。
具体的には、東京都道路交通規則の第10条第1項において電動自転車に幼児用座席を設置し、そこに乗せることができるのは「16歳以上の運転者が幼児(小学校就学前の者)を1人まで」と規定されています。
違反した場合には罰金や科料が科せられる可能性があり、罰金は最大2万円以下となります。
特に東京都内では交通量が多く狭い道も多いため、この規制は事故を未然に防ぐための重要なルールです。
他の自治体でも同様の規則があるか
東京都の規則は全国的に似たような法規制が存在しますが、各自治体によって若干の違いがあります。
たとえば神奈川県や大阪府でも同様の規則が設けられており、幼児用座席に乗せられる年齢が6歳未満に制限されています。
また、交通の混雑状況や自治体の交通安全方針によって取り締まりの強化や警告が行われることもあります。
一般的には電動自転車に幼児を乗せる際には全国的に同じようなルールが適用されるため、保護者は自分の住む地域の交通規則を確認し安全に遵守することが求められます。
日本自転車協会や警察のウェブサイトで、地域ごとの具体的なルールや取り締まり情報が公開されているため一度確認することをお勧めします。
特、都市部に住んでいる方、自転車の利用頻度が高い方は自治体の規則をしっかり把握しておくことが大切です。
実際に起こった交通事故の事例【2022年統計】
警視庁の統計によれば、2022年に電動自転車で小学生を乗せた際に起こった交通事故は36件報告されています。
この数字は近年増加傾向にある電動自転車関連の事故の一部であり、その多くがブレーキの制御ミスやバランスを崩した転倒が原因です。
特に都心部での事故が多く、交通量が多い場所や狭い道路で発生しています。
具体的には小学生を後部座席に乗せた電動自転車が急ブレーキをかけた際に転倒し、後ろに乗っていた子どもが頭部を強打したケースがあります。
このような事故ではヘルメットを着用していない場合、頭部へのダメージが深刻になることが報告されています。
また、事故に巻き込まれた歩行者への損害賠償も発生しており、法律を守ることがいかに重要かが浮き彫りとなっています
小学生を自転車に乗せた時の罰則・罰金

法律違反、ということで小学生を自転車に乗せると違反になります。
その具体的な内容もまとめ。
罰金の金額と具体的な法律
まず電動自転車に小学生を乗せることは法律で禁止されていますが、これに違反すると罰金が科せられます。
具体的には道路交通法第57条第2項に基づき、違反者には「2万円以下の罰金または科料」が科せられる可能性があります。
この規定は軽車両(自転車など)の運転者が法定の乗車人数や積載物の重量を超えた場合に適用されます。
電動自転車の幼児用座席に乗せられるのは「小学校就学前までの者」とされており小学生を乗せるとこの条項に違反することになります。
先ほども触れたように東京都道路交通規則の第10条第1項、16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児を1人乗せる場合、その幼児は「小学校就学の始期に達するまで」とされています。
この法律に違反した場合交通違反切符が切られ、罰金が科されることになります。
罰金は軽度の違反とされる場合でも2万円以下となり、罰金額は違反の状況や裁量によって異なりますが特に繰り返し違反を犯すと、罰金額が増加することもあります。
2万円以下の罰金だけじゃない!科料の可能性も
電動自転車に小学生を乗せる違反行為に対して科せられるのは罰金だけではありません。
場合によっては「科料」が適用されることもあります。
科料とは罰金よりも軽微な違反行為に対して科せられる経済的な制裁で、通常は1万円以下の金額が科せられます。
科料は比較的軽度な違反行為に対する処分であり違反の状況や初回かどうかなどが考慮されますが、交通法規を守らなかったことに対する法的な制裁として適用されることがあります。
たとえば電動自転車に小学生を乗せたとしても、事故や怪我が発生しない場合は罰金ではなく科料として処罰される可能性があります。
しかし科料も交通違反の記録に残るため、違反行為の積み重ねによってはさらに厳しい処罰に繋がる可能性があります。
科料が軽いとはいえ法的制裁を受けること自体が社会的な信用に影響を与えるため、できるだけルールを守り、違反を避けることが重要です。
電動自転車に小学生を乗せることの危険性

法律違反ということで実際に小学生を乗せると思った以上の危険性があるんです。
そんな危険性、もしもの際のケースを解説。
自転車に小学生を乗せる危険性
電動自転車に小学生を乗せることは重大な事故につながる危険性が高い。
まず小学生の体重は未就学児よりも重くなるため、自転車全体の重量が大幅に増えます。
たとえば電動自転車自体の重量が30kgだとして、そこに20kg以上の小学生が加わると50kg以上の重量を支えながら運転することになります。
これによりブレーキをかける際の制動距離が大幅に延び、特に急な停止が必要な場面で自転車が転倒しやすくなります。
また自転車の重量が増えるとブレーキをかけた際の制動距離が長くなります。
重い自転車を急停止させるのは通常の自転車よりも難しく、反応が遅れることで事故が起こりやすくなります。
特に急な停止が必要な場面ではブレーキが間に合わないことがあり、その結果として自転車が転倒するリスクが高まるでしょう。
さらに、子どもが乗っていることで、バランスを取るのが難しくなるためわずかな衝撃や道の凹凸でバランスを崩しやすくなります。
これも転倒の原因になります。
事故が起こった場合のダメージ・後遺症
そしてその事故が起こった場合のダメージもより大きくなります。
事故の多くはバランスを崩したり、急停止時にブレーキが効かずに転倒することが原因となっています。
また、幼児用座席に乗せられた子どもが怪我を負うケースも多く特にヘルメットをしていない場合には頭部へのダメージが深刻です。
こうしたリスクを避けるためにも、小学生を電動自転車に乗せることは法律で禁止されており、保護者としてこのルールを守ることが求められます。
事故の典型的なパターンとしてはバランスを崩して転倒したり、急停止時にブレーキが効かずに前のめりに倒れるケースが多いです。
特に幼児用座席に乗せられた小学生が頭を強打するケースがよく見られます。
もしヘルメットをしていなければ頭部へのダメージは深刻で、脳震盪やそれ以上の後遺症が残る可能性があります。
小学生向けの通学用自転車の選び方

上記の通り小学生になれば自分の自転車を持たせた方が安全、安心ということ。
そんな小学生用の自転車選びのコツもまとめています。
小学生用自転車はサイズが大事
小学生が安全に通学するためには自転車選びが非常に重要です。
そんな小学生向けの自転車を選ぶ際にはサイズが適切であることが最優先です。
一般的に小学生低学年の子どもの身長に合わせた自転車のサイズは14インチ~18インチが標準とされています。
中学年、高学年になると20インチ以上になります。
身長に合わない自転車を選ぶとバランスを崩しやすく事故のリスクが増大します。
特に都心部のような交通量が多い地域では、ブレーキ性能の良い自転車を選ぶことが重要です。
ヘルメットなどのプロテクトを買う
さらにヘルメットの着用は必須です。
2023年の調査によると小学生の自転車事故における頭部損傷率は全体の約50%を占めており、ヘルメットをしていればそのリスクは大幅に減少します。
他のプロテクターだとこの辺り。
またライトや反射材が付いているかもチェックポイントです。
通学時に暗い時間帯を通ることがあるため、自転車に明るいライトを装備することで周囲からの視認性を高め、事故を防ぐことができます。
購入後も定期的に自転車の点検を行いブレーキやタイヤの状態を確認することで、安心して子どもを送り出すことができるでしょう。
長い間乗ることができる自転車を買う
そしてコスパという意味では長い間乗り続けられるものがベスト。
小学生は体の成長が早いのですぐに買い替えなくてはならなくなるからです。
自転車のフレームが問題なくてもタイヤサイズがハマらなくなると買い替える必要があるので注意が必要です。
2Way、3Wayとよばれる自転車を購入すれば成長に従ってある程度対応可能。

補助輪の着脱、キックバイク、そして通常の自転車と変形できるためとてもコスパがいいです。
(キックバイクは地面を押してだけ進める自転車)
長く使っていきたい人はこういったキッズバイクを選びましょう。