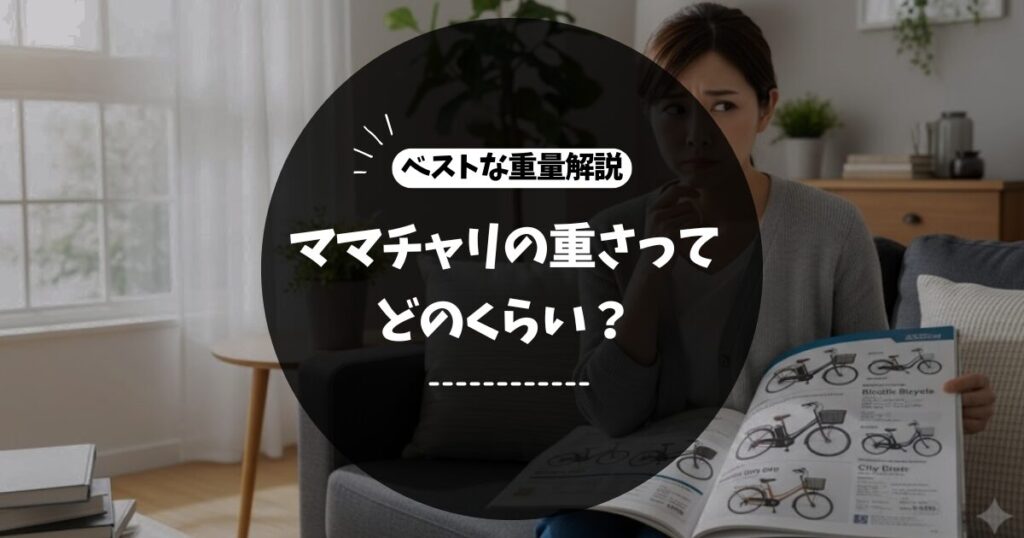こんにちは。電動自転車は究極のママチャリである、運営者の「yuri」です。
毎日の買い物や子供の送り迎えに欠かせない相棒といえばママチャリですが、いざ購入しようとカタログを見ると「ママチャリの重さ」が気になってしまいませんか。
「電動アシスト自転車は便利そうだけど、重すぎて駐輪場で扱えるか不安…」という悩みや、逆に「普通の自転車なら平均して何キロくらいが目安なの?」という疑問は、これから自転車生活を始める方にとって切実な問題です。
カタログに載っている20kgや27kgという数字だけでは、実際の駐輪場や坂道でどれくらいの負担になるのかイメージしづらいものですよね。私自身の失敗談や経験も交えながら、数値の裏側にある「体感的な重さ」について分かりやすくお話ししていきたいと思います。
データで見るママチャリの重さの平均と基準

自転車を選ぶとき、デザインや価格と同じくらい、いやそれ以上に大切なのが「重さ」です。
重さは毎日の快適さを左右するだけでなく、万が一の転倒時や駐輪場でのストレスに直結します。まずは、市場に出回っているママチャリたちが、実際にどれくらいの重量なのか、その平均と基準をしっかりと把握しておきましょう。ここを知ることで、自分にとって「重い」のか「軽い」のかの判断基準ができるはずです。
電動アシスト自転車の重さは平均何キロ
今や子育て世代や買い物メインの方にとって標準となりつつある電動アシスト自転車ですが、その重さは普通の自転車とは一線を画します。ズバリ言ってしまうと、電動アシスト自転車の平均的な重さは「27kg〜28kg」ほどになります。これはあくまで「標準的」なモデルの数値であり、チャイルドシート付きのモデルなどでは30kgを超えることも珍しくありません。
「えっ、そんなに重いの?お米3袋分!?」と驚かれるかもしれませんが、これには明確な理由があります。電動自転車には、普通の自転車にはない重量級のパーツがたくさん積まれているからです。
【重量増の主な原因】
・バッテリー:容量にもよりますが、これだけで1.8kg〜4kgほどあります。大容量モデルほど重くなります。
・モーターユニット:アシストの心臓部です。最近は軽量化が進んでいますが、それでも数キロの重量があります。
・強化フレーム:重い車体とモーターの強力なアシスト力に耐えるため、パイプが太く頑丈に作られています。
普通の自転車に比べて約10kgプラス、軽いロードバイクと比較すると約3倍もの重さがあるんです。乗ってしまえばアシストのおかげで坂道もスイスイ進みますが、「電源が切れたとき」や「駐輪場で持ち上げるとき」には、この27kgというズッシリとした重さを感じることになる点は覚悟が必要です。
普通のママチャリの重さと平均的な目安
では、電動ではない「普通のママチャリ」はどうでしょうか。こちらは概ね「16kg〜22kg」の範囲に多くのモデルが収まっています。

この幅の広さは、主にフレームの素材や装備品のグレードによって生じます。街の自転車屋さんやホームセンター、ディスカウントストアでよく見かける、1万円〜2万円台のお手頃なママチャリは、大体20kg前後だと思っておいて間違いありません。これらは「ハイテンスチール(高張力鋼)」という鉄の素材で作られています。鉄は非常に丈夫で安価ですが、比重が大きいためどうしても重くなってしまうのです。
一方で、少し価格帯が上のモデル(3万円〜5万円台)や、変速機などの機能を絞ったシンプルなモデルだと17kg台のものもあります。ただ、スポーツタイプの自転車(クロスバイクなど)が11kg〜12kgであることを考えると、普通のママチャリも「カゴ」「スタンド」「泥除け」「鍵」といった実用装備がフルセットで付いている分、それなりの重量はあると言えますね。
20インチのママチャリの重さは意外とある
「小さいタイヤの自転車(ミニベロ)なら軽いだろう」と直感的に思いませんか?実はこれ、ママチャリにおいては大きな誤解であることが多いんです。
特に電動アシスト自転車の場合、タイヤが20インチの小径モデルであっても、重さは約26.3kgほどあるケースが珍しくありません。カタログを見比べて「あれ?26インチとほとんど変わらない…」と気づく方も多いはずです。
これはなぜかと言うと、タイヤが小さくても大人が乗って安全に走るためには、フレームの強度を確保する必要があるからです。ホイールベース(前輪と後輪の間隔)を一定に保つためにフレーム形状が複雑になったり、パイプの肉厚を増したりすることで、結果的に車体重量は軽くならないことが多いのです。
【ここが注意点】
20インチだからといって、劇的に軽くなるわけではありません。バッテリーやモーターといった「重いパーツ」はサイズに関わらず搭載されているため、総重量はそこまで変わらないのです。
では20インチを選ぶメリットは何かというと、「軽さ」ではなく「重心の低さ」です。重心が低いとふらつきにくく、特に子供を乗せ降ろしするときの安定感は抜群です。重さの数値そのものよりも、この「安定感」や全長が短くなることによる「収納時のコンパクトさ」に魅力を感じるなら、20インチは素晴らしい選択肢になりますよ。
チャイルドシート付きママチャリの総重量
子育て中の方が最もシビアに気にすべきなのがここです。自転車本体の重さに加えて、チャイルドシートやその他の装備品の重さが加わると、総重量はとんでもないことになります。
例えば、安全性が高く人気のあるヘッドレスト付きリアチャイルドシート(後ろ用)は、それ単体で約4.4kg〜5kgもあります。もし20kgの普通の自転車にこれを取り付けると、それだけで25kg近くになり、電動なしでも電動並みの重さになります。
| 項目 | 重量目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 自転車本体 | 27kg | 電動アシスト標準モデル |
| リアチャイルドシート | 4.5kg | しっかりしたタイプ |
| お子様の体重 | 15kg | 3〜4歳児の平均 |
| 買い物などの荷物 | 3kg | スーパーの袋1つ分 |
| 総重量 | 49.5kg | 約50kgの負荷! |
さらにここに「レインカバー」や「ヘルメット」なども加わります。こうなると、もはや「自転車そのものの軽さ」を数キロ削るよりも、「その重さを支えきれる頑丈なフレームや、テコの原理で軽く立てられるスタンドか」という点の方が、安全面では圧倒的に重要になってきます。軽い自転車に無理やり重い装備をつけるのは、ふらつきの原因になり危険です。
安いママチャリは重い傾向にある理由
チラシなどで見る「9,800円!」といった格安ママチャリがなぜ安いのか、その最大の理由は「素材」にあります。安価な自転車の多くは、先ほども触れた「ハイテンスチール(鉄)」という素材で作られています。
鉄は安くて加工しやすく、とても頑丈という素晴らしいメリットがあるのですが、唯一にして最大の弱点が「重い」ことです。強度を出すためにパイプを厚くする必要があるため、どうしても重量がかさんでしまうんですね。また、安価なモデルはクランクやハンドル、スタンドなどのパーツも鉄製であることが多く、これも重量増の要因になります。
逆に、軽さを売りにしている自転車は「アルミ」や「クロモリ」などの軽い素材を使ったり、パーツ単位で軽量化を図ったりしているため、その分コストがかかり価格も高くなります。「軽さはお金で買う機能」という側面が、自転車の世界には確実にあると言えるでしょう。予算と相談する際は、この「重さの対価」をどう捉えるかがポイントになります。
軽いママチャリの重さを重視した選び方

「うちは坂道もないし、とにかく取り回しが楽な軽い自転車がいい!」「駐輪場が2段式の上段だから、軽いのが絶対条件」という方も多いと思います。
ここでは、重さを重視してママチャリを選ぶときの具体的なポイントや、注目の軽量モデルについて深掘りしていきましょう。
10kg台の軽いママチャリを探す方法
もしあなたが「どうしても10kg台のママチャリがいい」と考えるなら、普通のスペックのままでは見つけるのが難しいでしょう。何かを削るか、素材をグレードアップする必要があります。以下のポイントを押さえて探してみてください。
通販サイトなどで探す際は、これらの要素を組み合わせたモデルを探すと、17kg〜18kg台、あるいはそれ以下の自転車が見つかりやすくなります。ただし、装備を削るということは「便利さ」も少し減るということなので、自分の生活スタイル(夜間走行が多いか、荷物を載せるかなど)と相談してくださいね。
最軽量の電動アシスト自転車ビビSLの実力
「電動のアシスト力は欲しいけど、重いのは絶対に嫌」「高齢の親にプレゼントしたい」という方に、革命的なモデルがあります。それがパナソニックのショッピングモデル「ビビ・SL」シリーズです。
この自転車のすごいところは、電動アシスト自転車でありながら約19.5kg(20インチモデル・BE-FSL032)という驚異的な軽さを実現している点です。一般的な電動自転車が27kg前後ですから、実に7kg〜8kgも軽いことになります。これは普通のママチャリよりも軽いレベルです!
「カルパワードライブユニット」という大幅に軽量化されたモーターや、カーボン配合のバスケット、アルミフレームなど、グラム単位で徹底的に軽さにこだわって作られています。「重いから電動は無理」と諦めていた小柄な女性や高齢の方、駐輪場に段差がある方にとっては、まさに救世主のような存在です。
(出典:パナソニック サイクルテック『ビビ・SL・20 製品紹介』)
軽いママチャリはアルミフレームが鍵
軽さを最優先にするなら、スペック表の「フレーム素材」の欄を必ずチェックしてください。そこに「アルミ」と書いてあれば、その自転車は軽量である可能性が非常に高いです。
アルミは鉄の約3分の1の比重しかありません。もちろん強度を出すためにパイプの径を太くして作られますが、それでも鉄製の自転車に比べてトータルで3kg〜5kgほど軽く仕上がります。例えばブリヂストンの「アルミーユ」やミヤタの「クオーツ エクセルライト」といった有名な軽量シリーズは、アルミフレームを全面的に採用することで、24インチや26インチでも16kg台という軽さを実現しています。
持ち上げた瞬間に「あ、軽い!」とハッキリ分かるレベルの違いがありますので、毎日の出し入れでストレスを感じたくない方は、少し予算を上げてでもアルミフレームの自転車を選ぶ価値は十分にあります。また、アルミは錆びにくいというメリットもあり、長くきれいに乗れるのも嬉しいポイントです。
駐輪場での取り回しと重さの関係性
自転車の重さが一番のネックになるのは、実は「乗っている時」ではなく「降りている時」なんです。ここを見落として購入すると、後で大きな後悔をすることになります。
特に都市部のマンションの駐輪場でよくある「二段式ラックの上段」や「レール式のスライドラック」。ここに前輪を持ち上げてセットするとき、27kg〜30kgある電動自転車だと、女性の力ではかなりの筋力を使いますし、腰を痛める原因にもなります。また、混雑した駐輪場で自転車のお尻(サドルや荷台)を持ち上げて隙間にねじ込むようなシーンでも、重さはダイレクトに負担となります。
自分の駐輪場をチェック!
- ラックの上段に入れなければならない
- 駐輪場への入り口に段差やスロープがある
- 混雑していて、自転車を持ち上げて整理する必要がある
もしこれらに当てはまるなら、走行性能(バッテリー容量やギア数)よりも「持ち上げられる重さか?」を優先して選んだほうが、日々のストレスは劇的に少なくなりますよ。
26インチでも軽いママチャリはあるか
「26インチは大きいから重い」と思われがちですが、これも素材と設計次第です。先ほど紹介したアルミフレームのモデルであれば、26インチでも16kg〜17kg台のモデルは確実に存在します。
サイズが大きいことのメリットは、ひと漕ぎで進む距離が長く、段差の乗り越えも楽なことです。タイヤが大きい分、走行時の安定感も増します。身長がある程度ある方(目安として150cm以上)なら、無理にサイズを落として20インチや24インチにするよりも、26インチの軽量モデルを選んだほうが、走りの快適さと軽さのバランスが取れることも多いですね。
逆に、身長が低めの方は無理せず小さいサイズを選ぶことで、足つき性が良くなり、結果として「軽く感じる」ことにつながります。
結論としておすすめするママチャリの重さ
最後に、私なりの結論をお伝えしますね。あなたのライフスタイルに合わせて、許容できる「重さ」を選んでください。
まず、「坂道が多い」「子供を乗せる」「重い買い物荷物を頻繁に運ぶ」という方は、重さは覚悟して27kg〜30kg前後のしっかりした電動アシスト自転車を選んでください。この重さは「安定感」と「頑丈さ」の証でもあります。この場合、重さをカバーするために「両立スタンド」や「ハンドルロック」などの機能が充実しているかを確認しましょう。
一方で、「平坦な道がメイン」「駐輪場で持ち上げる必要がある」「自分一人で乗る」という方は、16kg〜20kg程度のアルミ製自転車、もしくは軽量電動の「ビビ・SL」クラスを強くおすすめします。毎日の数キロの差は、積み重なると大きな疲労の違いになります。
重さは毎日の使い勝手に直結する大切な要素です。ぜひ、ご自身の体力や生活環境に合った「ちょうどいい重さ」の一台を見つけてくださいね。
※本記事の数値は一般的な目安です。具体的な重量は各メーカーの公式サイトや製品カタログをご確認ください。また、オプションパーツの装着により重量は変動します。