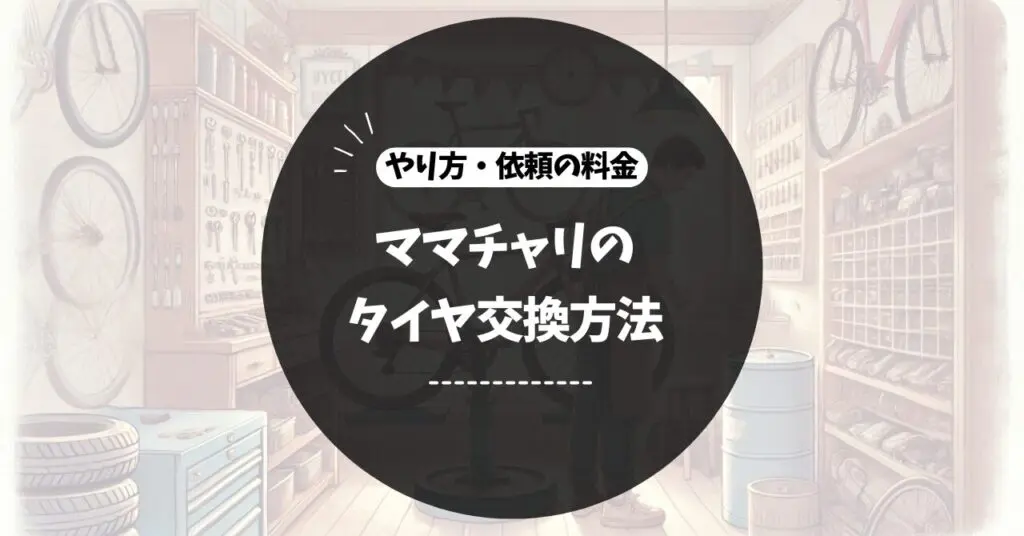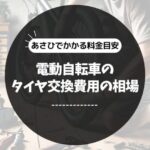ママチャリのタイヤ交換って自分でできる?
毎日の移動や買い物に欠かせないママチャリ。でも、パンクしたまま放置していたり、ゴムがすり減ったタイヤのまま乗っていたりしませんか?
実は、ママチャリのタイヤ交換は自転車屋さんに頼まなくても、自分でできる作業なんです。とくに前輪なら構造がシンプルで、初心者でもチャレンジしやすいのがポイント。後輪は少し手間が増えますが、やり方さえ覚えれば決して難しくありません。
今回は、前輪と後輪それぞれのママチャリのタイヤ交換方法を、必要な工具や注意点も交えてわかりやすく紹介していきます。自転車いじりが初めての方も、この記事を読めば「自分でやってみようかな」と思えるはずですよ。
ママチャリのタイヤ交換方法まとめ

自分で行うやり方・手順
ママチャリのタイヤ交換は自転車屋に頼まなくても自分でできる作業です。基本的な流れとしては以下の通りです。
- 自転車を逆さにして安定させる
- 車輪を外すために必要な部品(ナット、ワイヤーなど)を順に取り外す
- タイヤをリムから外し、チューブを交換
- 新しいタイヤ・チューブを装着
- 元通りに各部品を組み立てる
- ブレーキやチェーンなどの調整を行う
まず最初に行うべきなのは、自転車をひっくり返して作業台のように安定させることです。地面にハンドルとサドルが当たる形になるため、地面が傷つかないようにブルーシートや毛布を敷いておくと良いでしょう。この状態にすることで、車輪やブレーキ周りの作業が格段にしやすくなります。
次に、車輪を外すために必要な部品を順に取り外していきます。具体的には、ホイールの軸を固定しているナット類、ブレーキのワイヤー、チェーン(後輪の場合)などです。特に後輪は構造が複雑なため、取り外す順序を間違えないよう、事前に写真を撮っておくかメモを取ると安心です。
タイヤを外すときは、まず空気を完全に抜いてから、タイヤレバーを使ってリムからビード(タイヤの縁)を外していきます。片側が外れたらチューブを取り出し、劣化や損傷があれば新しいものに交換します。チューブはゴム製なので、使用していない間にも劣化が進みます。パンクしやすくなる前に、早めに交換しておくのがおすすめです。
その後、新しいタイヤとチューブを装着します。このときのポイントは、チューブがねじれたり、タイヤに挟まったりしないように注意しながら、リムに均等に収めていくことです。空気を少しだけ入れた状態にすると、作業がしやすくなります。
すべてが装着できたら、自転車に車輪を戻し、外した部品を順に取り付けていきます。最後にブレーキの効きやチェーンの動き、タイヤの回転のバランスなどを確認し、必要であれば微調整を行います。
前輪の場合
前輪はシンプルな構造なので、初心者でも比較的簡単に交換できます。
- 自転車を逆さにする
- ブレーキワイヤーを外す(必要があれば)
- ハブ軸のナットをメガネレンチなどで緩めて前輪を外す
- タイヤレバーを使い、タイヤを片側からリムから外す
- チューブを取り出して、新品のタイヤとチューブを装着
- 前輪を元に戻してナットを締め、ブレーキ調整を行う
ナットやワッシャーの順番は覚えておくと、戻す時に困りません。
後輪の場合
後輪はパーツが多く、取り外しもやや複雑です。ブレーキ、スタンド、チェーン、変速機ワイヤーなどを順に外す必要があります。
- 自転車を逆さにする
- スタンド、泥除け、リアキャリアなどを外す
- チェーンをギアから外して、適当な場所にひっかけておく
- バンドブレーキやブレーキワイヤーを外す
- 変速機のワイヤーを外す(下記参照)
- 後輪を取り外してタイヤとチューブを交換
- 全ての部品を逆の手順で戻し、ブレーキとチェーンの調整を行う
後輪は斜めになりやすいので、最後に車体に対してまっすぐになるよう位置を調整して締めることが大切です。
変速機のワイヤー外し方
内装3段変速のママチャリの場合、ワイヤーの外し方には少しコツがあります。
- ハンドル側のシフトを最も緩い(たるんだ)状態にする
- 後輪側の変速ユニットで、黄色いラインを目安にワイヤーをさらに緩める
- ワイヤー先端のパーツ(ナット付き)を回しながら引き抜く
- アウターケーブル(カバー)をユニットから引き抜く
内装3段変速のママチャリのタイヤ交換において、最も難所と言われるのが「変速機のワイヤー外し」です。この作業をスムーズに進めるためには、構造の理解と慎重な手順が必要です。以下に、それぞれの工程をより詳しく説明します。
まず、ハンドル側にあるシフター(変速レバー)を「最も軽いギア」に設定します。これは一般的に1速にあたるポジションで、この状態がもっともワイヤーがたるんだ状態になります。ワイヤーが張ったままでは後輪側の作業ができないため、最初にたるませておくことが重要です。
次に、後輪側のハブに取り付けられている「内装変速ユニット」を確認します。このユニットには、黄色いラインが2本付いているパーツがあり、これらのラインを一致させるように微調整する必要があります。ラインを合わせることで、ワイヤーにかかるテンションが最小になり、取り外しがしやすくなります。
ラインを合わせたら、ワイヤーの先端を見てください。そこには、小さな金属製のパーツが付いており、これはナットと一体になった「タイコ」形状の端子です。この端子を、軽くねじるようにして引っ張ると、ユニットからスルッと抜けるように設計されています。ただし、無理に力を入れすぎると部品が変形する可能性があるため、ゆっくりと様子を見ながら行いましょう。
端子が外れたら、次にアウターケーブル(ワイヤーのカバー部分)を変速ユニットから引き抜きます。ここまでで、ワイヤーは完全に変速ユニットから切り離された状態になります。アウターケーブルが引っかかって抜けにくい場合は、少し角度を変えてみたり、手前にたぐるように引くと抜けやすくなります。
作業に入る前や、取り外す途中の段階で、変速ユニットとワイヤーの接続部分を写真に残しておくと、後で組み立て直す際の参考になります。内装変速機は一見シンプルに見えても、正確な取り付けが求められるパーツです。ワイヤーの張り具合や位置が少しでもずれると、変速がうまくいかなくなったり、走行中にトラブルが起きることもあります。
以上のように、内装変速機のワイヤーを外すには、段階ごとに丁寧な確認と微調整が求められます。慣れればそれほど難しい作業ではありませんが、初めての場合は慎重に進めることが大切です。
必要な工具
最低限そろえておきたい工具は以下の通りです。
・メガネレンチ(14mm、15mm)
・プライヤーまたはラジオペンチ
・タイヤレバー(プラスチックまたは金属製)
・プラスドライバー(チェーンカバー用など)
・空気入れ(英式バルブ対応)
最初に準備したいのがメガネレンチです。前輪には十四ミリ、後輪には十五ミリのナットが使われていることが多く、それぞれに対応したサイズのレンチを用意する必要があります。メガネレンチはナットをしっかり六面で捉えることができるため、力をかけたときにナットを傷つけにくく、締めたり緩めたりする作業を正確に行えます。
次に必要なのはプライヤーやラジオペンチです。これらはワイヤー類の取り外しや、ネジを仮に固定したりする場面で活躍します。細かい部品を扱う際にも便利で、握力に自信がない方でも扱いやすいのが特徴です。
タイヤをリムから外す作業には、タイヤレバーを使用します。タイヤレバーはプラスチック製と金属製があり、リムの素材に合わせて使い分けることが重要です。例えばアルミリムであればプラスチック製のレバーが適しており、ステンレスリムには強度のある金属製が向いています。タイヤの側面にレバーを差し込んで、スポークに引っかけながら、てこの原理でタイヤのビードを浮かせていきます。
次にプラスドライバーの出番です。ママチャリのチェーンカバーや泥除けなどはプラスネジで固定されていることが多いため、ドライバーは欠かせません。サイズは二番が一般的で、持ち手のグリップがしっかりしているものを選ぶと力をかけやすくなります。
タイヤとチューブを交換したあとは、空気入れが必要になります。ママチャリの多くは英式バルブを採用しているため、それに対応した空気入れを用意しましょう。空気を正しく入れるためには、バルブの角度や位置に注意しながら、まっすぐ差し込んで注入することが大切です。空気圧の確認ができるゲージ付きのポンプであれば、適正な空気量を保てるので便利です。
さらに作業を快適にしたい場合は、ソケットレンチセットやT型ボックスレンチを揃えるのもおすすめです。ソケットレンチは狭い場所でも使いやすく、効率よくナットを回すことができます。またT型のボックスレンチは、トルクをかけやすく、押し込みながら回すことで固く締まったネジも外しやすくなります。
また、自転車を逆さにせずに作業したい場合には、専用の作業スタンドがあると便利です。スタンドを使えば車輪を浮かせた状態で整備ができるため、自転車本体に傷をつける心配が減ります。複数台の自転車を定期的に整備する家庭や、作業に慣れてきた方にとっては特に役立つアイテムです。
なお、よく家庭で使われるモンキーレンチは、一見便利そうに見えるものの、ナットを二面でしか捉えられないため、締めたり緩めたりする際にズレてナットを潰してしまうことがあります。こうなると工具もナットも使い物にならなくなってしまうため、モンキーレンチの使用はなるべく避け、専用サイズのメガネレンチを使うようにしましょう。
このように、必要な工具を正しく選び、用途に応じて使い分けることで、タイヤ交換作業の精度と安全性が高まります。初めての方は、まずは基本の工具から揃え、慣れてきたら便利な道具を少しずつ追加していくと無理なく整備に取り組めます。
それぞれを揃えるのが面倒という人は全てがひとまとめになったキットを買うといいでしょう。安いものであれば1万円以下で購入でき、タイヤ交換だけでなく自転車修理に関することは一通りできるようになります。
あさひに依頼する場合の料金・値段
全国展開している「サイクルベースあさひ」にタイヤ交換を依頼した場合の料金は以下の通りです(工賃のみ、部品代別)。
・前輪のタイヤ・チューブ交換:2,640円(税込)
・後輪のタイヤ・チューブ交換:3,960円(税込)
そのほか、パンク修理は1,430円(税込)から。車輪交換やホイール組み直しの場合は5,000円以上かかるケースもあります。
作業時間や料金は混雑状況や自転車の種類によって異なるため、事前に店舗に確認すると安心です。
ママチャリのタイヤ交換をする際の注意点

後輪を外さない方法の注意点
ママチャリの後輪を外さずにチューブを交換する方法は、スペースが限られた場所や、工具をあまり持っていない状況でも対応できる便利な手段です。しかし、便利な分だけ、作業時には細かな注意が必要です。
まず重要なのが、作業中にタイヤの片側だけをリムから外す工程です。この際に使用する「タイヤレバー」は必須の道具ですが、これを勢いよく差し込んだり、無理にこじ開けようとすると、中のチューブを傷つけてしまうことがあります。特に新しいチューブを入れる際は、外したばかりのタイヤのゴムが固くなっていて、力をかけすぎてしまいがちなので注意しましょう。
次に気をつけたいのが、新しいチューブのセット方法です。タイヤの中にチューブを押し込むときに、チューブがねじれたり、二重に折れた状態のままになると、空気を入れたときに内側で偏った圧力がかかり、すぐにパンクしてしまう原因になります。これを防ぐために、チューブを入れる前にほんの少しだけ空気を入れて、形を軽く膨らませてからセットすると作業がしやすくなります。
また、後輪を外さないことでスペースが限られるため、工具や手が入りにくく、無理な姿勢で作業することになります。この状態ではタイヤのリムやフレームの金属部分に手をぶつけたり、指を挟んだりするリスクもあるので、手袋や軍手を着用し、安全に配慮した状態で作業するのが理想です。
さらに、後輪はギアやチェーンが近くにあるため、作業中に油汚れが手や服につきやすいです。汚れても良い服装で作業し、チェーンやギアに余計な力をかけないよう気をつけましょう。
このように、後輪を外さずにチューブを交換する方法は、手軽さと引き換えに慎重な作業が求められます。初めての方でも落ち着いて一つひとつの工程を確認しながら進めれば、安全かつきれいに仕上げることが可能です。
サイズをしっかり確認する
タイヤやチューブを交換する際に最も重要なのが、「正しいサイズを選ぶこと」です。サイズが合っていなければ、せっかく購入しても取り付けられなかったり、無理に取り付けたことでタイヤのゆがみやパンクにつながる可能性もあります。
ママチャリに使われているタイヤのサイズは、一般的に「26 x 1 3/8」や「27 x 1 3/8」といったインチ表記になっています。このうち、最初の数字はホイールの直径をインチで示し、後ろの「1 3/8」はタイヤの幅を示しています。つまり、同じ26インチでも「1.50」や「1.75」など幅が違うと、ホイールに適合しないケースがあるので注意が必要です。

さらに混乱しやすいのが、ETRTO(エトルト)という国際規格です。例えば「26 x 1 3/8」はETRTOで「37-590」、「27 x 1 3/8」は「37-630」と表記されます。ETRTOでは最初の数字がタイヤの幅(ミリ)、後ろの数字がホイールの直径(ミリ)を示しており、より正確にサイズを特定できます。通販で購入する際や、互換性を調べるときにはこのETRTO表記を参考にすると失敗が減ります。
加えて、バルブの種類の確認も忘れてはいけません。ママチャリでは「英式バルブ」が標準ですが、スポーツバイクでは「仏式」や「米式」が使用されている場合もあります。空気入れのバルブ口が合っていないと、空気を入れることができなかったり、空気漏れを起こす原因にもなるので、自分の自転車に合ったバルブを事前に確認しておくことが必要です。
もしサイズの表記が読み取れなかったり、よく分からない場合は、スマホでタイヤの側面を写真に撮って、自転車店やホームセンターのスタッフに見せるのも有効な手段です。また、自転車ごと持ち込んで確認してもらうのも確実です。
正確なサイズとバルブタイプを理解し、それに合うパーツを選ぶことで、交換作業がスムーズに進み、走行時の安全性も高まります。
電動自転車の後輪の値段
電動アシスト自転車の後輪のタイヤやチューブ交換は、通常のママチャリに比べて費用が高くなりやすいです。モーターがホイール内に内蔵されているタイプでは、分解や取り扱いに専門知識が必要であり、工賃も上がる傾向があります
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| タイヤ代 | 2,000円 ~ 13,000円 |
| チューブ代 | 500円 ~ 3,000円 |
| 工賃 | 1,500円 ~ 3,000円 |
| 合計 | 4,000円 ~ 16,000円 |
一般的な交換費用の相場としては、タイヤ代が2,000円から13,000円程度、チューブ代が500円から3,000円程度、工賃が1,500円から3,000円ほどとなり、合計で4,000円から16,000円ほどかかることもあります。交換を依頼する場合は、購入店や電動自転車に対応した自転車専門店に相談するのが確実です。
初心者は結構面倒
タイヤ交換の作業は、前輪であれば比較的簡単で、初心者でも挑戦しやすい内容です。しかし、後輪となると話は別で、手順が複雑になります。なぜなら、後輪を外す際にはスタンドや泥除け、荷台、チェーンカバー、さらにブレーキワイヤーや変速機のワイヤーなどを外す必要があるからです。
取り外した部品を元に戻す際には、順番を間違えないことが重要で、さらにブレーキの効き具合やチェーンの張りなど、微調整も必要になります。このような点から、初心者にとって後輪のタイヤ交換は「思ったより大変」と感じることが多く、慎重さと根気が求められます。最初は前輪の交換から慣れていくのが良いでしょう。
交換時期は何年に一度か
ママチャリのタイヤ交換時期については、「おおよそ三年ごと、または走行距離三千キロメートル程度」がひとつの目安とされています。これは一般的な利用頻度を前提とした推奨期間であり、毎日短距離で買い物や通勤に使っている人、あるいは週に数回程度しか使わない人など、それぞれのライフスタイルによってタイヤの劣化速度は大きく変わります。
特に注意したいのは「使用環境」による劣化の進行です。例えば、屋外に駐輪している時間が長い場合、タイヤは直射日光、雨、風、気温差などの影響を強く受けます。紫外線によってゴムが徐々に硬化し、ひび割れが発生しやすくなったり、気温の変化によってタイヤの空気圧が変動し、偏摩耗の原因になったりすることがあります。そうなると、三年も待たずに交換が必要になるケースも珍しくありません。
一方で、きちんと屋内に保管され、使用頻度も少なく、適正な空気圧で維持されているタイヤであれば、三年以上使用できる場合もあります。しかし、たとえタイヤの外見がきれいであっても、ゴムの性質は経年劣化します。触ったときに弾力がなく、カサカサしていたり、指で押しても変形しにくいような場合は、表面が硬化している可能性があり、これも交換のサインといえます。
具体的な交換のタイミングを見極めるためには、以下のようなポイントに注意すると良いでしょう。
・タイヤのトレッド(溝)がほとんどなくなっている
・タイヤの側面や溝の中に細かいひび割れが見られる
・タイヤの表面が硬く、柔軟性が失われている
・乗っていて地面の振動が以前よりダイレクトに伝わる
・パンクの頻度が増えてきた
このような症状がひとつでも当てはまる場合、タイヤの性能が大きく低下している可能性があるため、安全面を考えて早めの交換をおすすめします。
また、タイヤを少しでも長持ちさせるためのコツとしては、定期的に空気圧をチェックすることが挙げられます。空気が抜けた状態で走行すると、タイヤと地面の接地面が増え、ゴムの摩耗が早く進んでしまいます。空気は少しずつ自然に抜けていくものなので、最低でも月に一度は空気を補充し、適正な空気圧を保つようにしましょう。
その他、雨ざらしや直射日光を避けるために、自転車カバーを使用するのも効果的です。屋外に駐輪する場合は特に、カバーをかけるか、なるべく日陰に停める工夫をすることで、タイヤや他のパーツの劣化を防げます。
タイヤの交換は安全に直結する重要なメンテナンスです。「まだ使えそうだから」と放置せず、定期的にチェックし、違和感があれば専門店で診てもらうのも一つの方法です。適切なタイミングで交換を行うことで、快適で安全な自転車ライフを維持することができます。